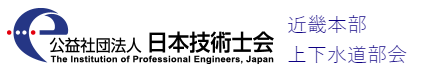近畿本部上下水道部会アーカイブス(編集中)
https://knksuidou.wixsite.com/archives例会記録
2025年度開催日
| 日付 | 開催日 |
|---|---|
| 2026年3月5日(木曜日) | 例会 18:30~20:00 近畿本部会議室 |
| 2026年2月12日(木曜日) | 例会 18:30~20:00 近畿本部会議室 第2週の木曜日 |
| 2026年1月8日(木曜日) | 例会 18:30~20:00 近畿本部会議室 第2週の木曜日 |
| 2025年12月4日(木曜日) | 例会 18:30~20:00 近畿本部会議室 |
| 2025年11月?日(木曜日) | 例会 18:30~20:00 もしくは見学会の予定 見学会の場合は日時未定 |
| 2025年10月2日(木曜日) | 例会 18:30~20:00 近畿本部会議室 |
| 2025年9月4日(木曜日) | 例会 18:30~20:00 近畿本部会議室 |
| 2025年8月7日(木曜日) | 例会 18:30~20:00 近畿本部会議室 |
| 2025年7月3日(木曜日) | 例会 18:30~20:00 近畿本部会議室 |
| 2025年6月5日(木曜日) | 例会 18:30~20:00 近畿本部会議室 |
| 2025年5月8日(木曜日) | 全体会18:00~18:30 例会18:30~20:00 近畿本部会議室 |
| 2025年4月17日(木曜日) | 見学会 PM「石川浄水場」(大阪府羽曳野市) |
2025/9/4
下水処理施設のトラブル対応
池川 耕司 技術士(上下水道部門)株式会社ウォーターエージェンシー
下水処理施設では、日常的にさまざまなトラブルへの対応が求められます。
本講演では、「異常流入水トラブル」「大雨による設備の故障」「処理水の水質異常」「大規模災害時の施設復旧」
の具体的な事例を挙げながら、それぞれの対応をご紹介します。
さらに、平常時におけるリスク評価と、緊急時の迅速な対応を、事業場と本社部門が連携して体系的に行う
「リスク&クライシスマネジメント」に関する弊社の取り組みについてもご紹介いたします。
2025/8/7
食品工場の排水処理における運用管理とトラブル対応について
星 邦明 修習技術者(上下水道部門) 公害防止管理者(水質関係第1種)
食品工場における排水処理の実務経験をもとに、現場で発生したトラブル事例とその対応策を紹介します。設備や処理プロセスの特徴、管理上の留意点、運用管理に関する個人的見解も交え、特に排水トラブル時の対応に焦点を当て、現場で役立つ実践的な知見を共有します。排水処理に携わる技術者にとって有益な内容を目指します。
2025/7/3
上下水道を一体にした経営改善方策
浦上拓也 教授 近畿大学 経営学部 経営学科 博士(経営学)
長引く経済低迷や人口減少など、上下水道事業を取り巻く社会環境は大きく変化しています。そのような中で市町村経営を原則とする水道事業、下水道事業は上下水道の組織統合が積極的に行われてきた一方で、水道広域化により組織統合された上下水道を再度分離するケースも増えています。2024年4月に厚生労働省の水道行政が国土交通省に移管されて以降、上下水道一体の取り組みを加速しようとしていますが、果たしてその方向性はどのようなものなのか?国の検討会・研究会での議論を踏まえ現状を解説します。
2025/6/5
井戸を用いた災害対応の実態
遠藤 崇浩 博士(法学) 大阪公立大学 現代システム科学域 教授
断水は日常生活や企業活動に大きな影響を与えます。このことは1995年の阪神・淡路大震災の経験で悲劇的な形で提示され大きな社会問題になりましたが、令和6(2024)年の能登半島地震被災地でも同じ課題が再び起きてしまいました。これを受け、井戸の重要性が見直されています。この報告では災害時における地下水利用の実態および課題を紹介し、強靭な社会づくりに向けた地下水ガバナンスのあり方をお話しします。
2025/5/8
水道施設の長寿命化へ高性能繊維シートによる構造物の補修・補強工法
石田 努 全国コンクリート水槽防食協会
水道施設のコンクリート構造物は、供給状況により「摩耗・腐食」等の様々な要因によって劣化が進行し、築造時の耐力が損なわれ、その耐久性が低下していく。薬品によるコンクリートの中性化や腐食の影響も考慮され、鉄筋の被りの増加や防食塗装が行われる。これらの劣化要因に抵抗する手段として、供用部の現況に鑑みて適切な「防食工法」を選定することが重要である。WICCビーバー工法は、水中接着技術と日本水道協会(JWWA)規格を組み合わせ、エポキシ樹脂による飲料水を処理する池状コンクリート構造物の表面防食を目的として開発された安全な工法である。コンクリート構造物の劣化に伴う補修・改修および補強工法として、炭素繊維と組み合わせて構造物の耐震補強に対応している。
2025/4/17
施設見学会「石川浄水場」(大阪府羽曳野市)
施設概要など2016年3月竣工(既設浄水施設をデザインビルド(DB)方式にて全面更新)
浄水量: 13,000m3/日
浄水プロセス: 直接濾過+紫外線 (旧プロセスは高速凝集沈殿+急速濾過)
内容説明: 石川浄水場は、DB方式で更新工事が発注され平成28年(2016)3月に竣工した浄水場です。原水は大和水系石川の伏流水で市の水道水の4割強を供給しています。今回の更新工事に際して水処理プロセスを従来の高速凝集沈殿+急速濾過方式から類似実績の少ない直接濾過+紫外線処理方式に変更しています。
2024年度開催日
| 日付 | 開催日 |
|---|---|
| 2025年3月6日(木曜日) | 例会 18:30~20:00 近畿本部会議室 |
| 2025年2月13日(木曜日) | 例会 18:30~20:00 近畿本部会議室 第2週の木曜日 |
| 2025年1月9日(木曜日) | 例会 18:30~20:00 近畿本部会議室 第2週の木曜日 |
| 2024年12月5日(木曜日) | 例会 18:30~20:00 近畿本部会議室 |
| 2024年11月7日(木曜日) | 例会 18:30~20:00 近畿本部会議室 |
| 2024年10月18日(金曜日) | 見学会 AMPM大飯発電所 (福井県大飯郡おおい町)JR新大阪駅からバス移動 |
| 2024年9月5日(木曜日) | 例会 18:30~20:00 近畿本部会議室 |
| 2024年8月1日(木曜日) | 例会 18:30~20:00 近畿本部会議室 |
| 2024年7月4日(木曜日) | 例会 18:30~20:00 近畿本部会議室 |
| 2024年6月6日(木曜日) | 例会 18:30~20:00 近畿本部会議室 |
| 2024年5月9日(木曜日) | 全体会18:00~18:30 例会18:30~20:00 近畿本部会議室 |
| 2024年4月11日(木曜日) | 見学会 PM「株式会社酉島製作所 本社・工場」(大阪府高槻市) |
2025/3/6
「上下水道職員の困り事を解決するDX 一体型クラウドシステム―官民連携、広域連携を踏まえた初心者でも対応に困らない仕組み作り―」
大峯 直樹 技術士(上下水道部門)
技術職員不足を解消する為に、DX活用による課題解決事例と、鹿児島県曽於地区で実施している広域連携の取り組みを紹介する。
2025/2/13
「有機フッ素化合物(PFAS)の汚染実態と除去・分解技術」
山村 寛 中央大学
国内のPFASの汚染実態および水質浄化、廃棄物処分についての概要について講演します。
2025/1/9
「日本技術士会近畿本部で学んだこと」
發田あずさ 日本技術士会 中国本部 会員
私は5年ほど前に日本技術士会中国本部に入会し、きんき本部でたくさんのことを学ばせていただきましたので、その中のいくつかを紹介したいと思います。また、私たちの生活になくてはならない上下水道のしくみ等について、部会のみなさまにご教授いただければ幸いです。
2024/12/5
「海水淡水化プラントの概要(中東実例を中心にして)」
岩橋 英夫 技術士(上下水道部門、総合技術監理部門) NPO法人JDA協会理事長
中東での実例を中心として海水淡水化プラントの概要を紹介します。海水淡水化プロセスを説明した後、蒸発法と逆浸透法それぞれのプラント実例を紹介します。その後活躍するプレイヤーや価格動向を紹介し、最後に今後の技術動向にも少し触れたいと思います。
2024/11/7
「上下水道用ポンプの現場での諸問題」
半田康雄 技術士(機械部門) 株式会社酉島製作所
現場で経験した次のような事例を紹介する①立軸斜流ポンプの異常圧力脈動
②両吹込みポンプの圧力脈動と異相羽根
③汚水ポンプの1/4波長管対策
④送水ポンプ2Fモータ振動の防振対策
⑤送水ポンプ遊動短管のゆるみ
2024/10/18
施設見学会「大飯発電所」(福井県大飯郡おおい町)JR新大阪駅からバス移動
詳細はホームページを参照願います。https://www.kepco.co.jp/corporate/profile/community/ooi/index.html
2024/9/5
「水道管内カメラ診断評価マニュアルを活用した水道管路の機能診断」
國實誉治 一般社団法人全国水道管内カメラ調査協会 専門会員 東京都立大学大学院特任准教授
・管内カメラ調査でわかること・管内評価方法について
・今後の取り組み
水道管内カメラ調査評価認定制度について
水道管内AI画像診断技術について
2024/8/1
「沈殿理論と沈降試験 -基礎理論は重要だ!-」
西崎柱造 技術士(上下水道部門) 京都技術士会 会員
沈殿池の理論除去率について調べるうち、粒子の沈降試験にたどり着いた。そこでは、粒子の粒径分布を求めるという異なる目的があったが、両者は、根っこのところではストークスの公式という基礎理論で結び付けられていることに気づいた。さらにストークスの公式は多くの粒径分布を求めるJISにも採用されていることも判明した。その一つが土木工事で利用されているJIS A 1204-2020「土の粒度試験」であった。
2024/7/4
「ステンレス・フレキ管による中小口径管路更新工法(SDF工法)」
福島大輔 SDF技術協会 事務局長
伏せ越し等の曲管を含む既設管路の内挿管工法であるSDF工法について、構造、性能、試験方法、施工計画及び施工の順に説明。
本工法に用いるSDF管は強靭であり、しかも柔軟な特性をもっていることから90°曲管も通過する。交通量の多い道路下の他、軌道敷下や河川を横断している既設管路の更新など、開削が困難な箇所に有効であり、しかもSDF管は耐震性を有していることから耐震化対策となる。
2024/6/6
「上水道及び工業用水道における官民連携事業の当社事例紹介」
松尾 晃政 技術士(上下水道部門) メタウォーター株式会社
(PPP本部 西日本統括部 部長 兼 アセットマネジメント推進部 担当部長)
会社紹介、上下水道事業のサプライチェーンの概説、業務委託からPPP/PFIに至る時流、形態、コンセッション方式の概要、ウォーターPPPをそれぞれ概説したうえで、講演者が管理する九州・山口地域のPPP/PFI事業の事例紹介を行う。ありあけ浄水場DBO、北九州ウォーターサービス(第三セクター)を核にした広域展開、荒尾水道包括委託(W-PPPLv3.5類似)、熊本工業用水道コンセッション(W-PPPLv4)の事例紹介と共に、スケールメリットを活かした統合的な管理の現状と将来像について紹介する。
2024/5/9
「クボタケミックス 高密度ポリエチレン製品のご紹介 ~耐震性向上・長寿命化・省力化を可能にします~」
中根健郎 株式会社クボタケミックス 西日本営業部 関西第一営業課
寺竹美穂 株式会社クボタケミックス 西日本営業部 関西第一営業課
「高密度ポリエチレン管」は、耐久性、耐震性に優れ、腐食や破損に強く、長寿命であり、施工方法が容易であるという特徴があります。また、製造時のCO2排出量が比較的少なく、環境負荷を低減できる配管材でもあります。インフラ市場では、水道用配水管・給水管として、民需市場では建築、消火配管材として採用が拡大しています。また、圧力配管に使用できる圧力用高密度ポリエチレン管は、耐候性を有し、露出配管が可能な製品となり、プラント・工場、省力発電、港湾・海洋等で採用が拡大しています。講演会では、製品の特徴や、採用実績等も含め、弊社の高密度ポリエチレン製品についてご説明させていただきます。
2024/4/11
施設見学会「株式会社酉島製作所 本社・工場」(大阪府高槻市)
詳細はホームページを参照願います。https://www.torishima.co.jp/outline/olinfo/au/
2023年度開催日
| 日付 | 開催日 |
|---|---|
| 2024年3月7日(木曜日) | 例会 18:30~20:00 近畿本部会議室 |
| 2024年2月8日(木曜日) | 例会 18:30~20:00 近畿本部会議室 第2週の木曜日 |
| 2024年1月11日(木曜日) | 例会 18:30~20:00 近畿本部会議室 |
| 2023年12月7日(木曜日) | 例会 18:30~20:00 おおきに会議室 |
| 2023年11月2日(木曜日) | 例会 18:30~20:00 近畿本部会議室 |
| 2023年10月18日(水曜日) | 見学会 PM「株式会社 島津製作所 三条工場 (医薬機器工場・分析工場)」(京都市中京区) |
| 2023年9月7日(木曜日) | 例会 18:30~20:00 近畿本部会議室 |
| 2023年8月3日(木曜日) | 例会 18:30~20:00 近畿本部会議室 |
| 2023年7月6日(木曜日) | 例会 18:30~20:00 近畿本部会議室 |
| 2023年6月1日(木曜日) | 例会 18:30~20:00 近畿本部会議室 |
| 2023年5月11日(木曜日) | 全体会18:00~18:30 例会18:30~20:00 近畿本部会議室 |
| 2023年4月6日(木曜日) | 見学会 PM「株式会社光明製作所」(大阪府和泉市) |
2024/3/7
「衛星画像解析が解決する新視点の漏水検知技術について」
加藤正純 ジャパン・トゥエンティワン株式会社 執行役員・豊橋本社支配人
人工衛星より取得した、衛星データの解析を以って、上水道での漏水疑いがある地点を半径100mにスクリーニングするイスラエルの解析技術を扱う国内代理店となります。
令和3年度。愛知県豊田市上下水道局の初採用を、きっかけに全国へ少しづつ知名度が広がり、成果も残せていることから、本年度までに、通算80事例。調査の圧倒的な時間短縮・調査距離の絞り込みなどが評価されている。また2年連続2度目の全域解析を事業化する水道事業体も誕生し、単に漏水疑いのある箇所の把握だけでなく、繰り返し起こる復元漏水箇所の把握が出来ることも、解明され、用途が広がりつつある。AIによる検出も行われていることから、確認された漏水箇所数が増えていこことで、更なる精度向上が期待される。
2024/2/8
「ステンレス鋼製水槽の特徴と耐震性」
行田聡(なめだ さとし) 森松工業株式会社 水道設計部
ステンレス鋼は、衛生性、耐食性、水密性、耐久性、強度などに優れた特性を備えている材料で、水道施設においてもステンレス鋼を用いた水槽が多く採用され、その優位性が高く評価されている。一方で、近年の大規模地震において矩形水槽におけるバルジングという振動現象が、ステンレス鋼製水槽の耐震性に対して影響を与えるとの報告がある。
本講演では、ステンレス鋼製水槽の特徴と、矩形水槽の耐震性について説明する。
2024/1/11
「既設浄水場の更新計画」
廣部裕彦 技術士(上下水道部門)(株)エフウオーターマネジメント
本講演では、既設浄水場(計画1日最大給水量3,000?/日:急速ろ過方式)の全面更新(土木・建築・機械・電気)とその水源である深井戸(計画取水量2,400?/日)の更新詳細設計について紹介する。この水源は、鉄・マンガンを多く含む水質であり、適切な浄水処理が必要であった。浄水フローは、深井戸→着水井→沈殿池→急速ろ過機→浄水池である。既設浄水場を運用しながらの計画であったため、施工ステップ・水運用計画に留意して設計を行ったものである。
2023/12/7
「工場排水規制の仕組み」
橋本隆 技術士 (上下水道部門)写測エンジニアリング株式会社(元 大阪市建設局)
工場排水規制は、放流先が公共用水域か下水道かによって適用される法律が異なり、また、特定施設という汚水発生施設の有無、排水量の多少によって、基準違反した場合の行政措置が異なる。さらに、都道府県の環境保全条例などよって、より厳しい排水基準が適用されることがあり、複雑な法体系となっている。本講演では、法体系について詳述し、大阪市の下水道を例にとり、立入調査の実際やその規制効果を紹介する。
2023/11/2
「下水道の価値」
中里卓治 技術士 (上下水道部門)環境システム計測制御学会
「変化を力に」は新内閣のキャッチフレーズです。下水道を取り巻く環境も大きく変化しています。その中で、下水道には不変の価値と新しく生まれる付加価値がありますが、今回は、付加価値に焦点を合わせて、下水から金が産出した話題と下水熱利用、下水道ブルーカーボンの話題を紹介し、これらに共通する下水道の特性を確認するとともに今後の可能性を論じます。
2023/10/18
施設見学会「株式会社 島津製作所 三条工場 (医薬機器工場・分析工場)」(京都市中京区)
詳細はホームページを参照願います。https://www.shimadzu.co.jp/aboutus/media/index.html#01
2023/9/7
「ミミズと排水処理」
赤木知裕 技術士(農業部門) 和歌山県工業技術センター
ミミズ(貧毛類)による汚泥削減技術の長期運用例は珍しい。演者らは、これまでに梅干し工場の排水処理施設において、水生貧毛類群集の優占種がウスベニイトミミズで、その密度が自然界でも類を見ないほど高いことを明らかにした。このウスベニイトミミズの生活史特性を知ることは、地球に優しい物質循環の手法を見つける糸口になるのではないかと期待している。本講演では、これまでに得られた知見の一部を紹介する。
2023/8/3
「水道事業のDX: ビッグデータ×AIによる配管破損リスクの予測診断」
前方大輔 Fracta Japan株式会社
水道崩壊という言葉があります。人口減少、一時期に集中投資した管路の維持管理費用等の増大、ベテラン職員による退職などによって水道を持続的に運営できなくなることを指します。この状況をできるだけ回避したいという想いの元、活動しているのがフラクタです。フラクタではAIと環境ビッグデータを活用して、水道管の劣化状態を診断しています。導入自治体の事例や効果など水道DXの最前線をお話しします。
2023/7/6
「山梨大学国際流域環境研究センター(ICRE)・スマート農業の取組み」
小谷信司 山梨大学教授・学長補佐・総合情報戦略部長 博士(工学)
山梨大学国際流域環境研究センター(以下、ICRE)の概略を紹介する。甲斐の国の治水技術の伝統が水工学として引き継がれ、分析化学や微生物学の専門家が加わり、水を中心とした環境研究が発展しICRE が設立された。次に山梨大学のスマート農業の概略を紹介する。山梨県は気候や地形が果樹栽培に向いていたことで、「ぶどう」、「モモ」、「すもも」の生産量が日本一である。山梨大学工学部では、果樹のスマート農業化を実施している。
2023/6/1
「日立造船の水・汚泥・資源化処理技術と脱炭素化への取り組み」
奥野芳男 技術士 (上下水道、衛生工学、総合技術監理部門)博士(工学)日立造船株式会社
水処理、再生エネルギー分野のし尿・汚泥再生処理事業、上下水事業、バイオガス事業において、曝気撹拌技術、リン回収技術、メタン発酵技術等の技術開発に従事。曝気撹拌技術に関しては、日本下水道事業団より技術審査証明書を取得し、有機性廃棄物からのリン回収技術やメタン発酵技術に関しては、日本環境衛生センターや全国都市清掃会議より技術評価書を取得し、開発技術の実装に貢献してきた。
2023/5/11
「地熱開発における抗井掘削上のリスク管理について」
上野修一郎 技術士 (応用理学部門)ドリコ株式会社
地熱開発事業の一般的な流れ、坑井掘削の概要を説明した上で、地熱開発事業の事業者ならびにコントラクターにとって最もクリティカルとなるリスク(逸泥対策)を取り上げ、実務上のリスク管理方法、今後の技術開発などの見通しを述べる中で、再生可能エネルギー事業の中で苦戦している地熱開発事業の実態の一部を共有し、リスクを正しく認識することの重要性を強調したい。
2023/4/6
施設見学会「株式会社光明製作所」(大阪府和泉市)
給水装置製作メーカーです。詳細はホームページを参照願います。https://www.komei-ss.co.jp/
2023/3/2
「上下水道で使用される水質分析機器について~イオンクロマトグラフを中心に~」
田中宏 技術士(電気電気部門) 株式会社 島津製作所
化学分析機器には、飲料水の水質分析、排水中に含有する化学物質の分析、汚泥の分析等、上下水道分野で活用される、様々な動作原理の様々な機器があります。本講演ではこれら機器の概要のご紹介と、特に講師の現在の担当業務であるイオンクロマトグラフ装置について、そのしくみや性能、使用上の注意などについて講演させていただきます。
2023/2/2
「道路における雨水浸水対策の取り組みについて」
菅野泰次郎 日之出水道機器株式会社 マーケティング統括本部
近年の集中豪雨による雨水浸水被害への対策には、下水道事業としての浸水対策だけでなく、道路における排水施設も含めたきめ細かな施設の設計と維持管理が重要であり、当社は鋳鉄の特長を活かしたものづくりと性能の可視化によって、効率的で実効性のある雨水対策をご提案しています。
2023/1/12
「中小規模の水道事業者が抱えている課題とその将来」
藤縄憲通 技術士(上下水道部門、総合技術監理部門)
日本の中小規模水道事業者の多くが抱える課題について、北海道最大の札幌市に隣接する北広島市を例に「ひと」・「もの」・「かね」の視点から抽出し、今後持続可能な水道事業として目指すべき将来について考察する。
2022/12/1
講演1 下水中のウイルス検査サービス
近藤貴志 中外テクノス株式会社 博士(工学)、技術士(生物工学部門/生物環境工学)
新型コロナウイルス感染症は未だ完全な収束となっていない。当社は、下水中のウイルス検査サービスを実施している。下水ウイルス検査は、感染リスクの高い高齢者養護施設の定期的なモニタリング(早期発見の可能性)や、下水道流域における感染状況(感染拡大・収束)の把握に適した検査と考えられている。今回、新型コロナウイルスを対象とした検査方法の概要と、ある施設における検査事例について紹介する。
講演2 アスベストに関する最新情報(法改正内容、事前調査方法、採取分析手順)
前原裕治 中外テクノス株式会社 技術部
大気汚染防止法(石綿障害予防規則)の改正内容の概要(有資格者の義務化等について解説)。事前調査方法、採取分析手順の概要、資料採取における注意点や資料採取量、分析方法の概要などについても解説。アスベストの事前調査、採取、分析機関の選定方法について解説
2022/11/10
日本にある朝鮮石人像と石造物
深田晃二 技術士(衛生工学部門) 深田技術士事務所
人間や動物の形をした石像は世界各地で見られる。日本には石仏・地蔵・狛犬などがある。又、日本の各地には朝鮮半島から渡ってきた石人像や石羊などが数多く見られる。朝鮮石造物は王陵や士大夫の陵墓の前の墓守として建てられたものだが、文字が刻印されていないので故郷を離れると由来が解らなくなる。日本での所在をまとめた文献が無かったので、朝鮮石人像達を訪ねて、それらの歴史を見てきた。
2022/10/6
環境へ配慮した林道づくり
福島智則 技術士(森林部門/森林土木) 兵庫県 但馬県民局 朝来農林振興事務所
兵庫県では、但馬地域などにおいて木材搬出を行うため車両が通行可能な林道の整備を進めています。林道は、豊富な森林資源及び自然環境の中を通過していますが、自然との共生が求められる背景から、環境保全へ取組んだ施設を設置することで、より自然に溶け込んだ林道整備を図っているところです。環境保全への取組みとして、法面保護や木材利用、小動物に配慮した構造物の設置事例などをご説明させていただきます。又、簡単ですが東日本大震災の対応経験についても紹介させて頂きます。
2022/9/1
「ドローンをはじめとするICT技術を用いた地下構造物点検手法」
嘉戸大治 技術士(上下水道・総合技術監理部門) 株式会社 エイト日本技術開発
地下河川(シールドトンネル等)、地下貯留施設(雨水調節池、立坑)は、市街地の雨水を貯留し、浸水防止を図る施設で大規模な構造物である。これらの施設の機能の維持のためには、定期的に内部を点検する必要がある。従来、目視により点検していたが、人員不足もあり、維持管理の効率化が求められてきていた。従来の目視による点検に代わり、ドローン等のICT技術を用いて維持管理の自動化、効率化を図る点検手法を紹介するものである。
2022/8/4
「プラント設計の事例」(浄水場及び下水処理場での事例)
平野大助 技術士(上下水道・総合技術監理部門) 平野技術士事務所
浄水場や下水処理場におけるプラント機械の施工事例を、具体的な設計手法や設計の注意点及びシステムを俯瞰した機種選定の重要性等を紹介させて頂きます。特に、新設案件が少なくなる中、見落とされがちなポイントを纏めてみました。又、簡単ですが東日本大震災の対応経験についても紹介させて頂きます。
2022/7/1
地震時の液状化対策と地盤災害対策としての排水の重要性
山口博久 技術士(衛生工学部門/総合技術監理)
地震時に発生する地盤の液状化について、現象の理解や耐震設計法の転換点となった新潟地震や阪神淡路大震災などの被害と液状化対策法について説明します。南海トラフ地震で想定される液状化の被害想定についても紹介します。講演の後半では、ケーススタディとして、静岡県熱海市で発生した土石流災害と大阪市西成区の擁壁崩壊を取り上げ、地盤災害対策としての排水の重要性とインフラメンテの必要性について説明します。
2022/6/2
「緩速ろ過は生物浄化法だった」
中本信忠 信州大学名誉教授 理学博士
2022/5/12
「微生物の世界~大腸菌からコロナウイルスまで~」
萩原由紀子 技術士(環境部門)アクア環境株式会社